建設人ハンドブック(2026年版)がリリースされました。
建設投資がこのところ順調に伸びていること、物価高騰も少し落ち着き、対応力もついてきたこと、採算性の改善が進んだことなどから、大手ゼネコンを中心に安定感が戻ってきたのでしょう。実際に、仕事はある、人が足りない、という声をよく聞きます。昨年の版では、新たな取り組みの方向性が多く提示された印象でした。今年は、それぞれの方向性について、検討会が立ち上がったり、ガイドライン等がリリースされたりして、具体化の端緒についたことを読み取ります。
懸念は、この景気が、大手だけではなく、広く中小企業全体に波及しているか、です。大企業にくらべて中小企業では、物価上昇スピードに見合う賃金上昇が難しいです。日銀が金融政策の枠組み見直しを宣言したのが2024年3月でした。それから1年半以上過ぎて、大胆な利上げに踏み出すことが出来ていません。日本経済には物価と賃金の好循環がまわり始めたとはいえ、全体として、まだ本調子とは言えない、との判断でしょう。この課題は、来年に繰り越し、ということでしょうか。
アメリカではトランプ大統領が誕生し、期待通りにひっかきまわされた2025年が、まだ終わっていませんが、ほぼ確定しました。建設機械などは、輸出で大きな影響を受けます。それ以外での影響は、あまり明確でない印象です。国際的な協力関係で推進される環境対策については、アメリカが消極姿勢に転じたため、停滞するかもしれません。しかし、考えようによっては、日本が努力次第で、自発的に足踏みするアメリカに追い付き、突き放す好機です。外国人材も、アメリカへの流入が細り、アメリカ国内からも優秀な研究者が流出する動きがあります。その流れを日本企業が活用する絶好のチャンスです。
今年も大きな気象災害が日本各地を襲っています。建設業は、復興作業の担い手としても重要です。いっぽう、慢性的な人手不足の中で、緊急時対応と日常業務との調整を迫られることが多くなっています。そのよう状況で、昨年4月、建設業にも適用された時間外労働の罰則付き上限規制のような労働規制に対する見直し機運が高まっています。バス、トラック業界などでも、運転手の確保が難しく、同様の問題意識が高まっているとか。ちょうど高市新政権が発足して、この問題に対する検討が指示されているようで、動向に注目しています。
『建設人ハンドブック2026年版』日刊通信建設新聞社
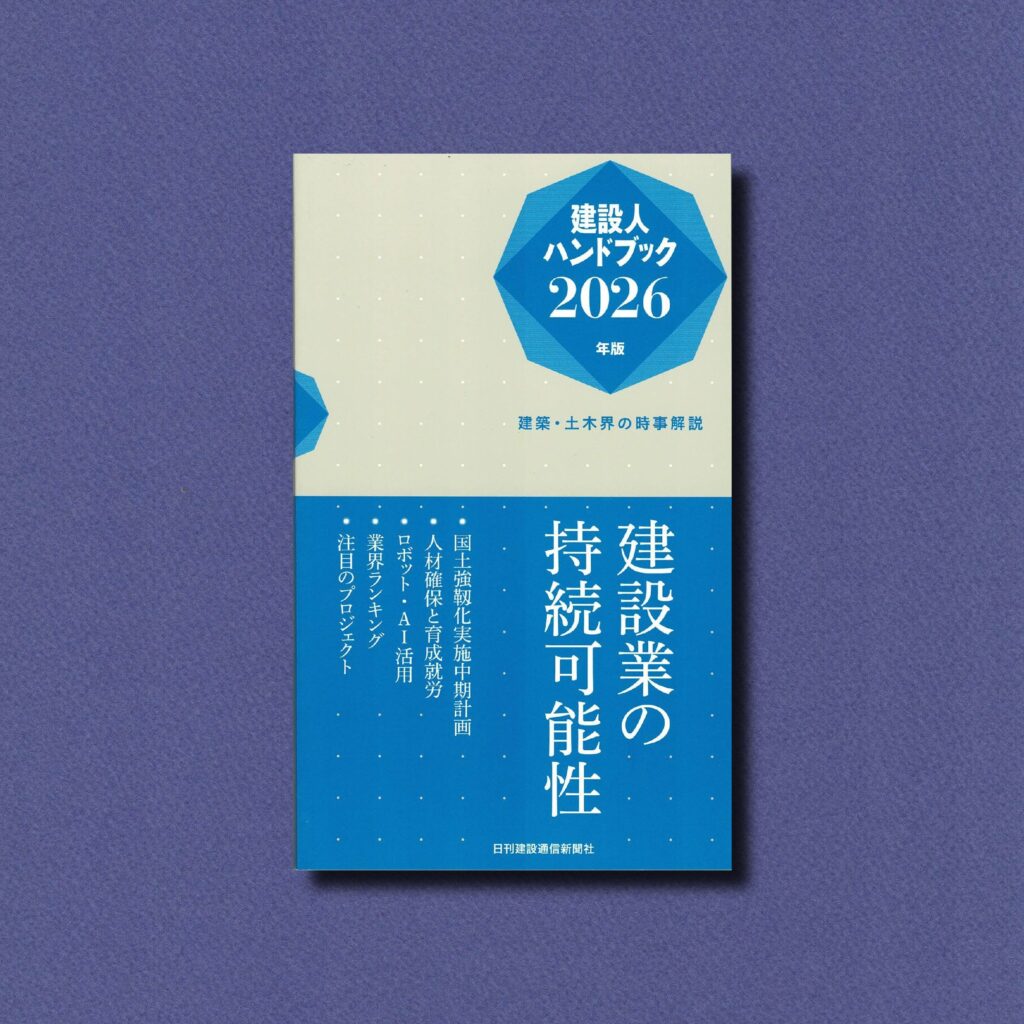
キーワード集
第1章
第1次国土強靱化実施中期計画
改正建築業法(第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について)
中央建設業審議会 労務費の基準に関するワーキンググループ
育成就労制度
骨太方針2025(経済財政運営と改革の基本方針2025)
中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画

